日本でパイル生地が使われるようになったのはいつ?
実は、意外と歴史があるんですよ。日本では明治時代の初めごろにパイル生地の元になる「再織(さいおり)」っていう織物が登場したんです。
再織?聞いたことないなあ。
和歌山県の高野口町で、前田安助さんっていう人がスコットランドの織物を参考にして考案したんですよ。作った生地を細く切って糸にして、またそれを織るという独特の技法です。
なるほど、ちょっと凝った作り方なんですね。その生地って何に使われてたの?
主に輸出用で、アメリカなんかではカーテンやテーブルクロスとして人気だったようです。
輸出してたんだ!じゃあ、今みたいなタオル生地のようなパイルっていつから?
それが発展して、大正時代くらいから「パイル織物」として進化していき、昭和初期にはドイツ製の織機が導入されて、本格的に量産できるようになったんです。
へえ、そんな昔からあったんですね。で、今よく見るタオルの生地もそれ?
まさにその「パイル生地」がタオルの定番素材なんです。糸をループ状に織ってあって、ふわっとしてて吸水性が抜群。お風呂上がりに体を拭くとき、あの気持ちよさはパイルならではなんですよ。
あのふわふわ感、たしかに気持ちいいですよね。
ループ状の糸が水分をしっかりキャッチしてくれるんです。しかも、ループの長さや密度を変えることで、柔らかさや吸水力も調整できるんですよ。フェイスタオル、バスタオル、ハンドタオル…どれもパイル生地が大活躍です。
なるほど、あのループがポイントなんですね。じゃあ、タオル以外にも使われてるの?
もちろんです。パジャマやバスローブ、赤ちゃん用のスタイなんかにも使われています。最近はサステナブル素材と組み合わせた「エコパイル」も注目されていて、環境にも優しいんです。
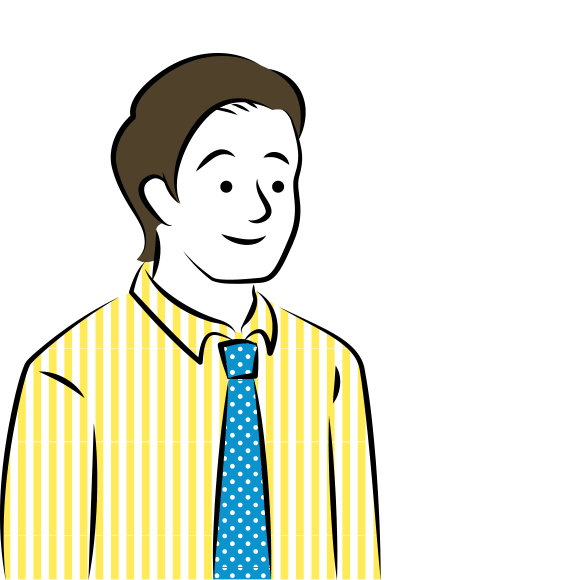
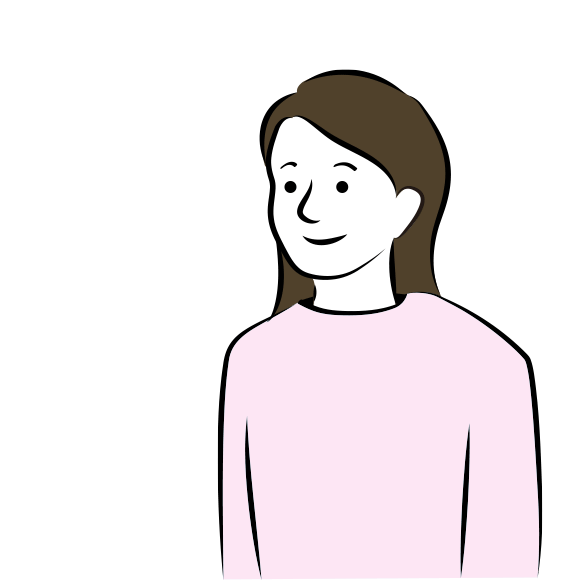
-
次の記事を読む

「糸番手」とはなに?
タオルの豆知識
パイル生地は、日本には昔からあったの?